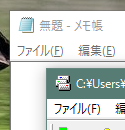まだ再現条件が全く不明ですが、Firefoxを44にした環境の一つ(Windows 7 x64)で、webが全く接続できない現象が発生しています。
43.0.4に戻すと問題ない
44のSafe Modeでも問題ない
アドオン全て無効でも回避できない
Firefox終了時にApplication Errorが記録される(アドレスは一定せず)
ただしntdll.dllの0x2e389、MSVCP120.dllの0xe439、unknownの0x15020249あたりは何度か見られている
44にした昨日は初回起動時のApplication Error(MSVCP120.dllの0xe439)以外は問題なかった
今日は.NET Framework 4.6.1を入れたが、念のため削除も現象変化なし
(システム復元はいつの間にか壊れており実施できず)
設定への何らかの新規追加項目が悪さをしていると想像されますが、当該環境はとりあえず43.0.4に戻して更新を止めています。
(追記2016/01/29)
どうもプロファイルではなくアプリケーションの問題のような? Prefs.js削除も効果無しでした。
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefoxにtobedeletedという残骸フォルダがありまして、それを削除したら読み込み不能は再現しなくなりました。ただ今度はFlash Pluginの実体(FlashPlayerPlugin_20_0_0_286.exe)が時々落ちています。
(追記2016/02/02)
ログオン後の初回起動しか正常動作しないことがわかりました。ただし、Safe Modeと管理者権限(怖い)での起動ではいつでも動作します。上記取り消し線の記述は、tobedeletedフォルダを管理者権限のファイル管理ツール(卓駆★)から削除した後、そのままfirefox.exeを直接起動したために起きたことのようです。
(追記2016/02/03)
ショートカットの置き場所により不具合が発生することがわかったのですが、条件がよくわかりません...。
タスクバーのピン留め(~\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar)やデスクトップだと再現し、スタートアップ含むスタートメニューだと再現せず、explorer以外からの起動(exe直接・ショートカット共)でも再現せず。
上記「初回起動」は初回でなくスタートアップだから動作していたのでした。しかし試行錯誤しているうちにタスクバーでも再現しなくなりました。一体何だったのやら。
43.0.4に戻すと問題ない
44のSafe Modeでも問題ない
アドオン全て無効でも回避できない
Firefox終了時にApplication Errorが記録される(アドレスは一定せず)
ただしntdll.dllの0x2e389、MSVCP120.dllの0xe439、unknownの0x15020249あたりは何度か見られている
44にした昨日は初回起動時のApplication Error(MSVCP120.dllの0xe439)以外は問題なかった
今日は.NET Framework 4.6.1を入れたが、念のため削除も現象変化なし
(システム復元はいつの間にか壊れており実施できず)
設定への何らかの新規追加項目が悪さをしていると想像されますが、当該環境はとりあえず43.0.4に戻して更新を止めています。
(追記2016/01/29)
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefoxにtobedeletedという残骸フォルダがありまして、それを削除したら読み込み不能は再現しなくなりました。ただ今度はFlash Pluginの実体(FlashPlayerPlugin_20_0_0_286.exe)が時々落ちています。
(追記2016/02/02)
(追記2016/02/03)
ショートカットの置き場所により不具合が発生することがわかったのですが、条件がよくわかりません...。
タスクバーのピン留め(~\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar)やデスクトップだと再現し、スタートアップ含むスタートメニューだと再現せず、explorer以外からの起動(exe直接・ショートカット共)でも再現せず。
上記「初回起動」は初回でなくスタートアップだから動作していたのでした。しかし試行錯誤しているうちにタスクバーでも再現しなくなりました。一体何だったのやら。